前回のエントリでは、 VTuberの岸嶺ミミムさん(Twitter)、思惟かねさん(Twitter)との3人で行った座談会の書き起こしを公開しました。
2021年1月の時点でVTuber業界について語る、全3回の配信でしたが、前回のエントリが「第2回」の配信内容にあたります。
そのエントリも好評だったということで、今度は第3回から長めに書き起こしたいと思います(なお、前回も含めて他のお2人に確認していただいた上で、読みやすく加筆・再構成したテキストになっています)。
どちらも座談会というより、泉がこの配信のために準備した初出のアイディア(他では未発表)をプレゼンしていたパートを切り取っており、「VTuber論」に興味のある人に広まればいいなと思います。
- プレゼンのお時間 ~オタクの「好みの構造」とVTuber~
- キャラクター論の虚構とリアル
- VTuber語りと「ぼくら語り」の話
- 外見と内面、虚構とリアルのマトリクス図でVTuberを位置付けられる!
- 全体の締めくくりと、図の下側の解説
- 図の右側の解説
- 終わりに
- 元配信アーカイブ&切り抜き版動画
- これ以外のおすすめVTuber記事
プレゼンのお時間 ~オタクの「好みの構造」とVTuber~
ミ 昨年(2020年)を振り返りつつ、これからのVTuber業界を予測する座談会も、この第3回で最後となります。そのなかでも第1回では「VTuberとアバター」についての考え方を、第2回では「VTuberとタレント」についての考え方をメインにしてきました。
- 第2回から部分的に書き起こした前回のエントリ:誰も語ってこなかった「VTuberアイドル論」【配信書き起こし】 - izumino’s note
ミ 実はまだ、泉さんが話し切れてない部分があるんですよね? それが、KAI-YOUの記事のこの部分だと。
泉 記事のスクショが今出てると思うんですけど。

ミ はい。(引用部分を読み上げる)VTuberというジャンル自体、オタク界で流行しているように見えて、実際は「二次元オタク」からしても、「顔出しのアイドルや声優のオタク」からしても、違和感を根強く持たれており、その中間的な波長に合うタイプだけがハマりやすいという人を選ぶ性質がある……。そのオタク内における好みの構造だけでも別に論じる価値がありそうなのだが、……ということですよね?
泉 はい。繰り返し言ってることですけど、「VTuberブーム」というものの渦中にいるとやっぱり、それだけで業界を見てしまう。熱中しているだけの視点になってしまう。
思 あ~、そうですよねぇ……。
泉 「嫌ってる人は勝手に嫌ってれば?」という無関心な態度にもなりやすいですし。「VTuber界がすごく盛り上がってる」っていうのは、内側の実感としてはそうかもしれないですけど。だからVTuberに届くマシュマロとかでよく見かけるのが、「布教したいけど興味持ってくれません!」
ミ はは(笑)。
泉 よく聞きますよね。学校なり、職場なり。VTuberは求心力とか、熱中させる力……単純に言えば動員力ですよね。いわゆる「ファン忠誠度」というものはすごく高くなりやすいと思うんですけど。
ミ うん。
泉 基本的にぼくは、「VTuberにハマる人」って波長がちょっと変わった人だと思っていて。
思 ほぉ。
泉 たぶん若い人たちが中心になりやすいというのも、変わった波長を受け入れやすいからだと思うんですけどね。今までのオタク文化に「特別染まってない」人であるほどハマってくれやすい。あるいは元々「受け入れる幅の広い」人か、たまたま「波長の合った」人なんだと考えています。
ミ このKAI-YOUの記事は、「渦中にいると見えるものが違ってしまう」と仰る通りで、そのなかで一歩引いたというか、もっと客観的に見ていく必要があるんじゃないかってことですよね。
思 VTuberから一歩引いてというのはそうなんですよね。ただ、こう、もうひとつ広げて見ようとした時に、どういう枠組みで見ればいいのか。私は正直ピンとこなかったんですよね、実際。
泉 じゃあ、次の図を出してほしいんですけど。
ミ えっと、外見と内面のやつですね。

泉 二次元キャラ、VTuber、リアルというのをみっつ並べた上で、「外見」と「内面」で分けるんですけど。まず「二次元キャラ」っていうのは全部作り物ですよね? 絵だし、その思考や感情の中身は全部人が考えてるし。
ミ うんうん。
泉 で、「リアル」っていうのは、まぁ「生モノ(ナマモノ)」とか呼ばれてるジャンルで。リアルアイドルでもいいし、声優でもいいですけど。リアルの肉体と心を持った現実の人間ですね。誰かの考えた人格ではなくて、現実に姿を見ることができるし、「内面は本人のものである」という意味ですね。
ミ なるほどね、はい。
泉 その中間にある「VTuber」というのは、「外見は絵である」と。見た目は作り物。でも「内面はリアルである」と。まぁ、そうではないVTuberというのもいると思いますけど、「内面が個人に結び付いていて、本当にある」ということですね。
思 ふむふむ。
泉 だから「VTuberの二次創作は生モノに近い」と言われるのも、そう。まぁ、仮に二次元キャラの不謹慎な絵を描いたりしても、怒る人は怒る……原作者とか、ファンは不快な思いをするかもしれませんが。VTuberの場合は、本人が怒る。「本人が嫌な思いをするからやめましょう」って文化がある。
思 ありますね~。本人に見られないように、わざわざTwitterでブロックしてからエッチな絵を描くとか聞きますね。
ミ それは特殊ですねえ。普通の二次元キャラにはない話ですもんね。
泉 この文化にはプラスの面もあって、絵描きさんにとっては、自分の描いたファンアートを本人が「いいね」してくれたり喜んでくれたり、配信に使ったりしてくれるなんて、「二次元キャラではありえないことだ」って凄く感動したりするんですね。
自分がキャラデザした娘からバレンタインにチョコもらうとか………そんなこと存在するの……?これは夢か……?輝夜月ちゃん……こんな幸せなことあるのか……現実に…??ありがとうございます…生きていけるわ……🍤🍫
— Mika Pikazo (@MikaPikaZo) 2018年2月13日
- これはファンの絵師ではなく、VTuberの「生みの親」をVTuberが喜ばせた例(豆知識だが、生みの親の「ママ」呼びを定着させたのも輝夜月である)
ミ あ~~~、ありますよねぇそれ。
泉 ここまでの話でも、「リアルに寄るか、作り物に寄るか」でメリットとデメリットの両方が生まれてるんですね。本人がいるおかげで、ありえないほど喜ぶ絵師さんもいれば、肩身が狭くなる絵師さんもいる。
ミ 確かに。面白いですね、それはリアルに独特というか……。当たり前ですけどね、相手がいる話なので。
泉 他の「推し」文化……。いわゆる「推し」っていうと、タレントでもいいですし、キャラクターでもいいですけど、推しの文化にVTuberを位置付けようとした場合、「外見」と「内面」にそれぞれ、「虚構」と「リアル」が混ざっているのが見分け方になるんじゃないかなと。
思 ふぅ~む。
キャラクター論の虚構とリアル
泉 そう考えると分かりやすい。で、ぼくは漫画研究が専門なので、関係の深い分野として「キャラクター論」というのがあるんですけど。そこでも「(二次元キャラが)どのくらいリアルに近いのか」「(生モノが)どのくらいフィクションに近いのか」を分析するのが、最近の流行になってるんですね。
ミ&思 ほお~~。
泉 そういう難しい話を抜きにしても、オタクの世界では「公式の設定は受け手側で解釈違いを起こすよりも、ある程度ちゃんと決まっていたほうがいいよね」「パラレル設定やマルチエンドじゃないほうがいいよね」っていう、一回性を尊重する考え方が、00年代の終わりから10年代の始めあたりになって強く出てくるんですよね。
(ここで「バーチャルYouTuber可憐」や「『シスター・プリンセス』から『Baby Princess』への変遷」の話にしばらく脱線……)
ミ 「解釈違い」って言葉は、よくオタクの話題にのぼりますよね。
思 ですねぇ。
泉 だから10年代は時が進むにつれて、キャラクターに統一見解的なものが求められていった流れがあったなと。で、ぼくのお友達で、漫画研究者の岩下朋世さんっていう方がいるんですけど。彼が去年(2020年)出した、『キャラがリアルになるとき』というキャラクター論の本があるんですね。
泉 これタイトルからも、なんとなく主旨が分かってくると思うんですけど。作り物であるはずのキャラクターが、リアルに近付くことで、「推しが尊い」みたいな、実在の芸能人と同じように語ることもできるようになってくると。
ミ はいはいはい、ありますね。

泉 ただですね、岩下さんは多少ぼくが、VTuberの基本的な知識を直接レクチャーしたことはあったんですが、基本VTuberを追ってない人なので。この本のあとがきでも「本書では残念ながらバーチャルYouTuberを扱えていない」と断っていて、本人も取りこぼしを認めてるんですが。実際ね、「VTuberを入れて語ったら全然違う話になるだろうな~」って感じるくだりも結構多いんですよ。
思 なるほど。
VTuber語りと「ぼくら語り」の話
泉 こういうキャラクター論と、VTuber論をうまく結び付けられるといいんですけどね。で、ぼくとしては、VTuber界の実態とか実感をちゃんと踏まえて考えたいと思ってます。ただ、「ファンの素朴な感想」みたいなものを重視するだけでもないっていうのは、KAI-YOUの記事を読めば解ってもらえると思うんですね。
ミ はいはい。
泉 そのー、「研究者だか学者だかが何言ってんだ」という視点とセットで、逆に「ファンが素朴に語ってるだけでいいんだ」って考える素朴論があるんですけど。でもその素朴論で行ったところで、「好きなものを内部から語ってるだけだよ」っていう問題を指摘してるわけですね。
ミ 前々回の配信(1:46:12~)でも、漫画の評論に「ぼくら語り」という問題があったという話をされてましたよね。
泉 そう、「ぼくら」という共同体をファン同士で作ることによって、その「ぼくら」以外の視点というのを無視してしまう、なかったものにしてしまうのが「ぼくら語り」と呼ばれたっていう話ですね。
思 私も、もうちょっと視点を広げて、VTuberシーンのなかであまり語られていないところを、次は書いていきたいなと思いつつも、なかなか情報収集できないんですよね。
泉 思惟かねさんの記事でVTuberシーンを「トップランナー層」「チャレンジャー層」「アマチュア層」に分けていたように、トップランナー(ここでは大手企業勢のこと)の寡占状態のなか、みんなでそれにチャレンジするか傍観している……、という見立ては説得的でとてもいいと思うんです。
2020年のVTuber業界はどう変わったか(前編:3つのトレンドとデータから見える変化)|思惟かね(オモイカネ)
泉 でも、別のところで自立して、成功している事例に目を向けることもできると思うんですよね。
ミ ふむふむ。
泉 VTuberファンが興味ないだけで、安定的に人気を得ていたりするので。だからKAI-YOUの記事で紹介していたのが、バーチャルジャニーズやHoneyWorksのLIP×LIPですけど。HoneyWorksのプロジェクトでいうと、先月(2019年12月)に劇場アニメが公開されるくらいになっているのに、バーチャルジャニーズが出演することを「知らない」わけですよ。
ミ ほとんどの人は注目してませんよね。
泉 VTuberファンは語らないし、VTuberメディアの記事になったりもしない。逆に『アニメージュ』や『アニメディア』とか、アニメ誌系のメディアには載るんですね。そうするとお互いに、バーチャルタレントの仲間だとは認識しないわけですよね。
ミ あ~、なるほどね。
泉 ファン同士の流動も起こらないし、それって双方に得のない話だと思うんですけど。
思 そうですよねぇ……。お互い刺激を与えられるところとか、なんだろ、「こっちはあんまりだな」って思った人がそっちに行ったりとかね。本来だったらコンテンツに合わなくて離れるだけの人が、移動してくることもあるでしょうから。
ミ それはVTuber界が情報過多というのもあるんですかね?
泉 情報過多……。うーん、KAI-YOUのぼくの記事で「誤読されてるかな」って感じていた部分もありまして。それは「VTuberの数が多すぎて追いきれないよ」っていう単純な話だと思ってる人が多そうだな、と。ぼくも個人勢や新人VTuberが大量に存在していることは認識してますし、それらを追って応援することには意義があると思います。ただ、そういう頑張って掘り返さなきゃ埋もれてしまいそうな対象じゃなくって、劇場映画になったり、アニメ誌の表紙を飾ったりとか、記録に残る活動しているのに、「それを仲間に入れないのはなんなん?」みたいな話なんですよね。
通称“ナナニジ”は、アイドルとバーチャルアイドルの二足のわらじを履き、メンバーそれぞれが各担当キャラクターを持つ。2017年9月にデビューし、直近ではオリコン週間シングルランキング4作連続2位と人気急上昇中。
22/7、『MUSIC BLOOD』出演決定 2次元と3次元を行き来する14人組アイドル | ORICON NEWS
ミ あ~~~。なるほどね、なるほど。
思 SNS的に言うと、「クラスタが違う」って状態なんでしょうねぇ、完全にね。……ちなみに聞いてみたいんですけど、泉さんはどういうところを見ていればチェックできると思いますか? こういうものは。
泉 どうだろう? でもこの後、「VTuberと似てるけどちょっと違う」みたいな、個別の作品やコンテンツというのはまとめて紹介しますので。
ミ おっ!
泉 さすがに、それぞれのコンテンツを自分がどう知ったかまでは詳しく思い出せませんけど。みなさんも頑張ってくださいというか、これからメディア側が頑張ってほしいですけどね。
ミ あー、それはそうですね。
思 もうちょっと、横断的にね。
泉 つまり、YouTubeやSNSのレコメンド機能、関連付けのアルゴリズムだけでは解決できてない問題だからこそ、今こうなっているわけですよね。だとしたら、ポータルとなるメディアが関連付けを超えて頑張るしかないです。「アルゴリズムの奴隷になってはいけない」がおそらく令和のテーマではあるので(笑)。
ミ 確かに(笑)。それは非常に重要なところですよね。
外見と内面、虚構とリアルのマトリクス図でVTuberを位置付けられる!
泉 やや脱線していたので話を戻しますと、クラスタの違いというだけではなくて、単純な「好き嫌い」の問題がオタクにはありますよね。しかし、好き嫌いの話ってあんまり、表立ってしない部分もあって。わざわざ敵を作りに行くような話ですしね。ただ、オタクの好き嫌いがそれぞれのジャンルの特徴を凄くよく表していることもあって、見逃すわけにもいかないな、という考え方をぼくはしています。
ミ ほうほう!
泉 じゃあ、次の図を。いわゆる四象限を使った、マトリクス図ですね。

泉 縦軸・横軸で、「外見がリアルに近いか」「内面がリアルに近いか」っていう四象限に分けるとこうなるっていう図です。つまり図の右上が「全部リアル」で、左下が「全部作り物(虚構)」ってことになりますね。
ミ うん、え~と、順に左上が「2.5次元」、右上が「生モノ」、右下が「アバター」とVTuber、左下が「二次元キャラ」と。
泉 まぁ2.5次元って言葉も、VTuber界では混乱させやすくて。そういう自称をするVTuberもたまにいるんですが、こうして見るとド反対方向にいるんですよ。
思 ふ~む?
泉 ここで言う2.5次元っていうのは、テニミュであるとか、最近では刀剣乱舞とかありますけど、「2.5次元ミュージカル」の舞台を指してます。「二次元のキャラクターをリアル(三次元)の人間が演じますよ」という。衣装とかのビジュアルを二次元に寄せることで、リアルの舞台を見ながらも、キャラクターを幻視しながら重ねて見ることができるという意味で、「完全なリアルでもないですよ」っていうジャンルですね。
思 はあ~、それで2.5次元って言うんですねえ。
泉 で、演じている役者はリアルだし、公演を何日も続けていくなかで役者が成長していくというドラマも確かにあるんですが、そこで演じられている役(キャラクター)というのは、「漫画やゲームのキャラですよね?」っていう。
ミ あ~~。

泉 ここで2.5次元は、分類的に分かりやすいから左上の位置を代表させましたが、まぁ他の舞台や実写のキャラクターも、みんなここの位置になっていくでしょうね。つまり「外見はリアルの役者」で、「内面は作り物のキャラクター」。まぁ、演じている役者に内面があるにしても、だいたいキャラクターの内面とは分けて考えるわけでして。
ミ ふんふん。
泉 たまにそこを分けられずに、混同してしまう熱心なファンが出たりはしますが。それも許されることではなくて、まぁ普通なら問題視されますからね。いい例なのが、ハリウッド俳優のアンソニー・ホプキンスがハンニバル・レクター(役)と同一視されすぎるっていう。
ミ はっはっは(笑)。ありますねーそれ。
泉 インタビュアーとかに、さんざん「人肉食べたことありますか?」って聞かれすぎて本人はウンザリしてるっていう(笑)。よくない話ですよ。
思 チャットのコメントでもありますが、例えばアイマスライブはどこに来るのかな? とか。「すとぷり」はどこに来るのかなとか。リスナーのみなさんも結構、分類に悩んでらっしゃるようですねえ。
泉 じゃあ次の、最後の図版を出してください。今回のメインコンテンツですね。
ミ はい、出しまーす。

泉 みなさん気になっているのは、結構入ってるんじゃないかと思うんですけど。すとぷりは(右端中段に)入ってますし、アイマスライブとは書いてないけど「二次元声優アイドル」という括りに入れてます。ちなみにこの画像は全部、公式アカウントのTwitterアイコンを使わせてもらってます。だから真ん中にあるのはラブライブのアイコンなんですけど。
ミ うんうん。この図はどうやって見たらいいんですか?
泉 「なんでそれぞれのアイコンがその位置にあるのか?」の細かい説明は後でするとして、大きくどういう風に見ればいいかというと、それぞれのコンテンツの分類っていうだけじゃなくて、それぞれのコンテンツを愛好しているオタクの分類でもあるんですね。
ミ へえ~~~っ。
泉 コンテンツだけじゃなくて、それぞれにファンがいるんだっていうのを重ねて見てほしいんですけど。例えば左下の「二次元キャラ」のところには、二次元オタクがいるわけですよね。反対に右上のカドには、アイドルオタクとか、芸能人ファンがいる。2.5次元コンテンツには2.5次元オタクがいる。その近くにある「実写キャラ」には「魔法ワールド」シリーズの公式アイコン(※当時)を使ったんですが、ハリポタ以外にも『ロード・オブ・ザ・リング』のキャラクターの二次創作が好きな人たちもいて、女性に多いですけどね。最近の洋画だと『キングスマン』の人気も近いかな。
ミ あと『SHERLOCK(シャーロック)』! ベネ様ですね、ベネ様。
思 へえ、そういうのに多いんだあ。
泉 最後に右下ですが、最近はコンテンツが飽和……たくさん提供されていることで、バーチャル関係のものが非常に混雑していますけど。
ミ 右下にすごく集中してるみたいな感じになってますね。
泉 で! ぼくが一番伝えたいのはですね、あのー、二次元オタクっていうのは、右方向にも上方向にも、みんな嫌ってるんですよ。

ミ ……嫌ってる?
思 ああ……。
泉 右側も、右ナナメ上も、真上もみんな、何かしら嫌う理由がある。これ、なんて説明すればいいかな。自分の話で説明しようかな。子ども頃の感覚なんですけど。
ミ はい。
泉 子どもの頃って、テレビでスーパー戦隊見るじゃないですか。当時のぼくって、戦隊の「スーツを着ているシーン」を見るのが好きだったみたいで。変身前の役者が出てくると、それは見たくないな、早く変身してほしいなって思う子だったんですね。
ミ ああ、早く戦闘になってほしいって、そういうことですか?
泉 いや、「人間の顔を見たくなかった」が正しいですね。
ミ うお(笑)。
思 あー。
泉 これ、発達心理学で説明できることなんですけど、子どもの感じている世界ってあまり現実的じゃないんですよね。丸っこくて、それこそぬいぐるみのような世界っていうのを子どもは持っていて。だからお母さんとか、女の人の丸っこい顔を見せると子どもは大人しいけど、髭面の大人の顔を見せると泣き出す、っていうイメージありません?
ミ ああっ、なるほどね……。
泉 ディテールが濃ければ濃いほど、「見慣れないもの」になっちゃうんですね。サンタクロースくらいヒゲもじゃでモコモコしてたら、逆に丸っこく見えるでしょうけど。カドが少なくて丸くって、テクスチャのないものほど見やすいんですよ、子どもの世界って。
思 だからアンパンマンとか……。
泉 そうそう。生まれた時に「目が2つに口があれば人間の顔である」とか、原始的な「モノを見るモデル」は認知機能として持ってるんですけど。
- 画像はWikipediaの「シミュラクラ現象」から
泉 実際に、「生まれて初めて見る外の世界(現実)」というのを、写実的に、解像度の高い映像そのままで認識するかというと、それは「少しずつ慣れる必要のあるもの」なんですよね。
ミ そうなんだ? じゃあ、子どもの頃の記憶があやふやで、顔もあんまり思い出せないっていうのも関係してるんですかね。
泉 まぁ、そもそも人間の脳は「写真のように」見たものをそのまま記憶してるわけではない、っていう事実もあるんですが。だから、子どもに何か教えたい時には、人形劇をやったりとか、動物の絵を描いたりとか、現実をデフォルメしたもので説明したほうが、「子どもの世界に近い」ことになるんですね。
思 学習まんがとかそうですね。
泉 世界的に、アニメとか漫画っていうのは「卒業」するものって観念があるのはそういうことなんですよね。歳を重ねるごとに、写実的な世界に慣れていくことで大人になって、発達するんだっていう考え方が支配的だから。だから丸っこい絵の世界、デフォルメされた世界っていうのはそこまで辿り着く前の「補助輪みたいなもの」って認識のされ方をしてるんですね。文化的には。
ミ なるほど! それは……、ぼくも今まで日本の漫画に対して、大人だとか子どもだとか言われることに凄く違和感があったんですが、そういう認識をされてるんですね。
Scott McCloud, Understanding Comics: The Invisible Art Scott McCloud, Understanding Comics: The Invisible Art
- ちなみにアメリカの漫画研究においても、「シンプルな線の絵は心の世界を表し、複雑な(写実的な)線に近付くほど外の世界(現実)を表す」という分析が行われている
泉 日本で「二次元」の文化って凄く成熟しているので、大人の人がハマるなんてことはいくらでもありますけど、元々はその、丸っこい絵の世界から、子どもの頃の絵の世界をずっと持ち続けている人がオタクなクリエイターになっていった、という面はあるんだと思いますね。それは別に「幼い」って意味じゃなくて、「幼い部分を残しながら大人になっていった人」がオタクなわけです。
ミ ふんふんふん。
泉 ま、だからこそ二次元でエロを描いたりもするわけですよね。二次元の世界を残したまま、大人になっていくというのは、そういうことでもある。
ミ あぁ、あ~~。
泉 そこで、オタクでも性格が色々と分かれてくるんですけど。三次元をずっと嫌ったまま二次元コンプレックスになるタイプのオタクと、「三次元も魅力的だし、どっちもいいじゃん」ってなるオタクもいる。で、「子どもの頃は少女漫画とか好きだったけど、全然読まなくなっちゃったな」ってなって、今は芸能人にハマっている、とか。
ミ はいはい。
泉 主にこのみっつがあって。ぼくはまぁ、結果として雑食的な感じになっちゃったんですけど。
思 はあ~~~。私それで言うとまさに、あんまり現実の、三次元って好きじゃないタイプですね。VTuberとかは見れますけど、「YouTuber」は好きじゃないんですよね正直。人の顔が映ってると、なんか抵抗感があります。
泉 アバター文化の世界でも、写真取り込みのようなリアルアバターを使う人と、二次元的な美少女アバターを好む人に分かれてて、それは派閥というか流派というか……。フォトリアルなアバターはやっぱり、思惟かねさんは得意じゃない感じですか?
思 うーん、そうですね。どちらかというと、ちょっと違和感がありますね。
泉 だから、映画の『レディ・プレイヤー1』で描かれていたようなVRの世界は、主にリアルアバターを使う文化になっていて……って、実写映画だからそれは当たり前っちゃ当たり前なんですが(笑)。
ミ それはそうですね(笑)。
泉 CGの世界、仮想現実の世界であっても、写実を踏襲するっていうのが、どちらかというとアメリカ的な、欧米的な視覚世界かもしれなくて。
ミ あー、なるほどね。
泉 逆に、我々のいる日本の視覚世界っていうのは、あんまり二次元と三次元を融合させたがらない性格があるとぼくは思っていて。面白いのは、今ホロライブにハマっている英語圏のオタクというのは、自分でも顔出しで配信してることがあるんですね。たぶんTwitchのストリーマーなのかな。その海外ファンに日本語の字幕を付けた切り抜きを見たりするんですが、「日本のオタクは顔出しで推しの話なんかしねえよ」って思いません?
みのむし Minomushi - YouTube
- ※ホロライブ以外の動画も混ざってます
思 確かに!!
泉 でも向こうのオタクは、顔出しで二次元の話をしてるんですよね。
ミ そうですね。アニメの第何話の感想、みたいなリアクション動画って、海外ではだいたい顔出しの方がやってらっしゃいますもんね。

思 うーん、言語圏の違いを感じますねえ。
泉 日本のオタクが顔出しで二次元の推しを語ってると、リアルじゃない世界の話をしてるのに、「余計なもん見せんな」って気になりやすそう。ちなみに、図の左端の中段にいるのが「バーチャルヒューマン」のimma。「CG画像なんだけど、フォトリアルな仮想の人物」っていうジャンルですね。横軸で言えば「内面は作り物」だから左端にいて、縦軸では「外面は作り物だけどリアル」だから位置的にこのあたりかなって。
泉 あとまぁ、ぼくは「雑食だから両方アリ」みたいな言い方さっきしましたけど、正直には「どっちのオタクの気分にもなれる」んですよ。なんでかというと、一方のジャンルにハマっている時はそこにコミットしちゃうんですね。二次元を見てる時は「俺は萌えオタだ」って気分になるんですよ、アイデンティティとしては。「やっぱ二次元だよな」って気分になる。でも、リアルのアイドルを見ている時は「やはり生モノはいいな」って風に、頭が切り替わっている。その「切り替わる瞬間」というのが、自分のなかにあるんですね。
ミ ほうほう。
泉 だから、アニメキャラをずっと見ていた直後に、現実の人間の顔をパッと見ると、なんか「グロ画像」っぽく見える気がする時があるんですよ(笑)。
ミ あー、ははは(笑)。
思 あ~~っ。
泉 生モノっていうだけで、なんか気持ち悪く見える。逆に、VTuberの配信をずっと追い続けていた時に、欲しい物があってアニメ専門店に入ったんですが、その瞬間にもヘンな感覚があって。
思 ほう。
泉 どういう感覚かというと、店内に美少女キャラのスタンドパネルとかポスターとかが大量にあるわけですけど。「あれ? これ全員生きてないんだよな」ってなる(笑)。
ミ ははは(笑)。
- これは生きている
メロブ日本橋店で草
— 響狐🌽 (@ability_Resound) 2020年10月4日
前はグラちゃん作ってましたね pic.twitter.com/dwr5YEx3VE
- こっちは生きてない(?)
メロンブックス日本橋店はエスカレーター横の狭い位置にあったよ〜扱いわるw 最初気づかんかったわ(´∀`)
— kuro_ss (@kuro_ss) 2018年12月1日
#金恋GT応援 pic.twitter.com/7yT27NljtR
泉 生きているVTuberと違って、「こいつら実際は生きてないんだよな」って。生きてないキャラクターが大量に並んでる光景を見て、なんか気持ち悪いなっていう。いや別に、そんな感覚が「おかしい」ってのは自分で分かるんですよ。アニメを見ている時はちゃんとキャラクターが「生きている」と感じながら楽しんでますから、本気でそう思ったわけではない! ただ、ジャンルを横断する時に、こういう違和感が生じるってことが想像できるんですよね。自分のなかの感覚として。
ミ なるほど。それってオタク趣味にかぎらず、国とか文化をまたぐ人でも起こりやすそうな話ですね。
泉 で、重要なのは、この話の前に「外野やアンチの意見なんか無視すりゃいいんだよ」、「ファン同士で好きな話してればいいんだよ」みたいな話じゃないんですよって断っておきましたよね。なんでかっていうと「嫌われている要素」が、その魅力をそのまま表している所があるので。裏表になってるんですよ。
思 ああ~~。
ミ なるほど、魅力のある部分が表裏一体なんですね。おもしろ!
泉 その嫌われ方っていうのは、ただの厄介クレーマーというか、「クッソどうでもいい些細なことに、お前ら不快感を覚えやがって」とか、「どうでもいいだろ」って言いたくなるような所ではなくて。ファンにとって凄く魅力のある、そのジャンルの特徴を表した所がピンポイントで反感を持たれているケースがある。
ミ 我々が素晴らしいと思っているポイントが逆に、外からは嫌悪感の対象になっているという。
思 なるほど~。
ミ それは今回こういう、様々な視点から総合して初めて分かるというか、認識できるとも言えますね。そりゃすごいな。
泉 そうですね。「外見」の視点だけで見てみれば、「フォトリアルな見た目のグロさ」とか、視覚的な嫌悪感に繋がりますけど。「内面」の視点で言えば、VTuberを好きな人って多分、「(推しが)生きてるってなんて素晴らしいんだ」ってみんな思ってるはずなんですよね。
ミ うんうん、うんうん。
泉 生きた内面があって、作り物じゃない人格がある。生きているから、絵を描いたら喜んでくれるし、コメントしたら反応してくれる。応援で生活を楽にしてあげれば、そのぶん活動で返してくれる。頑張りすぎて時には傷付くこともある。それは内面がリアルだから。
ミ うん。
泉 楽しいことも辛いこともひっくるめて「内面がリアルということは素晴らしいことだ」ってなるんですけど、逆にそれって、作り物のなかに「真実」を見出してきた二次元オタクからしてみれば、その牙をもがれているような気分になる。
ミ それはうまい言い方だな。なるほどね(笑)。
泉 作り物のなかにこそ、キャラクターの真実がある。そういうプライドを持って俺たちオタクはやってきたはずなのに、何をそんな「絵の付いた生主」みたいなやつらに誘惑されてるんだ、ってなる。「そいつらの内面は生主と同じなんだろ、俺たちが嫌ってきた人間なんだろ?」っていう。
ミ あ~~、「お前が心のなかに持っていた嫁はどこに行ったんだ! そいつはお前の嫁じゃない!」ってことですね(笑)。
思 あはは、そうですよねえ(笑)。
泉 だから彼らにしてみれば、VTuberが醜聞とかを起こすとめちゃくちゃ溜飲が下がるわけですよ。それって実際はごく一部の出来事にすぎないし、なんならVTuberオタクも性格の悪い人間を非常に嫌う傾向があるんだけど、そんな好意的に考えようとはしない。VTuberが何かやらかす度にメシウマになるというか、胸がすく思いになる。「言ったじゃん! そいつらは人間だって。人間には裏切られるってことは分かってたじゃん」
ミ ああ~~。
泉 VTuberのコミュニティからすると、そういう他ジャンルからネガティブなイメージダウンを仕掛けてくるオタクにこそ「生々しい人間の悪意」が象徴されているように感じるでしょうけどね。だから、流石に直接は言わないんですよ。VTuberファンに表立って言わないんだけど、こっそり思ってる。ぼくの(VTuberとは関係のない)Twitterタイムラインを見ててもそれは感じますけどね。
ミ これは、泉さんのアンテナが広すぎる感じがしてきましたね。ぼくはそこまで外の目を気にしないですもん。
思 それは同じくですね。VTuberを見ていて、なかなかそういう見方にはならないですよね。
泉 でもVTuberって、ここ3年くらいのブーム(※当時)なわけで。「みんな3年前までは普通に二次元オタクをやってたんじゃないですか?」って、ぼくは思いますけどね。ってことは、二次元ジャンルのフォロー関係って、あんまり切れないと思うんですけど。
ミ はいはいはい。
泉 ってことは「自分が所属してるクラスタのなかで自分だけがVTuberにハマってて、他のみんなはアイマスやラブライブにハマったままなんだけど」って人も多いと思いますけど(笑)。
ミ なるほど。でも「両方」って人もいますよね。VTuberも好きで、二次元も依然好きで、って人もいますけどね。
泉 (チャット欄を拾って)いい指摘をされてますけど、「でもキャラは裏切らないけど公式は裏切るんですよね・・・」(一同笑)

ミ いやあ(笑)。
泉 キャラの性格を公式が台無しにするケースなんて散々なほどあって。それに凝りたオタクは「VTuberなら本人の意志が何よりも尊重されるんだ!」と感銘を受けやすい。これは、奴隷が鎖を自慢しあってるみたいになってて、どっちもどっちなんだけど(笑)。相手を下げて、こっちのほうがマシだっていう。
ミ そういう意味だとこのコメントは、どっちも分かる立場で書かれてるんですよね? VTuberファンの言い分も、二次元オタクの言い分も理解できると。
泉 もちろん、どっちがいいって話ではなくて。両方に酸いと甘いがある。両方の性質をちゃんと分かった上で、好みに合わせて楽しめばいいっていう。
ミ 今までの話を聞いた感じだと、VTuberを好きになる人って、オタクとしては寛容性の高い人たちなのかなって思ったんですけど、そういうわけでもないんですか?
泉 VTuberはまだ新しいジャンルですから、若い人が集まりやすいですし、寛容性というだけでなくて……。
思 単に、他のジャンルを知らない?
泉 VTuberに反応してもらえただけで、「一生推していきます!」みたいに先の分からないこと言っちゃう人って、まぁ若いじゃないですか。若いのか……まぁ本当に耐性がないのかもしれないけど。いい大人になってそういうのは。
ミ まぁそうですね。
泉 逆に、アイドルオタクのプライドっていうのは、そこで心をしっかり保つことにあるわけで。実際、アイドルオタクのあいだで「ガチ恋」ってあんまりいい意味で使われてないですからね。恋愛の感情が芽生えること自体はいいんだけど、そういう自分を制御できてない人に対する、侮蔑的なニュアンスもある。
思 確かになんかこう、「一線を引いてとにかく活動を応援している」という人のほうが、手慣れたアイドルファンという感じがしますよねぇ。
泉 で、印象操作として、二次元オタクの立場からすれば、VTuberファンとか、生主にハマる人とか、アイドルオタクっていうのはみんな「耐性のないチョロい人たち」であったほうが都合がいい、気分はいいわけですよ。人間に騙されやすい人たちであったほうが、「いや俺たちは人間に騙されないから正しいんだ」ってなれる。
ミ なんかそれもなあ(笑)。
泉 ぼくがここまで熱く語っているのは、二次元オタクとしてのプライドっていうのも凄く分かるからなんですよ。二次元オタクっていうのは、基本プライドを持ってやるもんなんですよね。
ミ そうなの?(笑) いや、確かに。
泉 で、二次元オタクには、二次元オタクなりに「現実と虚構を区別して踏み越えないため」の倫理観が強くて……。だって、たいていの二次元キャラには現実の声優がつくじゃないですか。
ミ そうですね。
泉 昔、庵野秀明監督も言ってたんですが、「アニメは何もかもが作り物の世界だが、そこに唯一、ナマの要素が入ってくるのが声優の声である」と。まぁ庵野秀明も実際、かなり声優オタクっぽい一面を持ってたんですけど。
ミ はいはいはい。
泉 で、「キャラクターは作り物であり、我々は作り物を愛しているんだ」っていうテイで行くなら、そこにナマの声優、中の人がいるとしたら、どう処理すべきか考えるべきってことになる。つまり声優さんも「作り物に参加しているスタッフの1人である」という解釈に落ち着かせないと、うっかり声優さんを好きになってしまうわけですよ。
ミ うっかり好きになる人、結構多いと思うんだけど(笑)。
泉 好きになってもいいけど、そこに一線は置きましょうと。声優は「キャラクターに息吹を吹き込んでくれる存在」でしかなくて、逆に言えば、「声優さん自身もキャラクターに敬意を払っていてほしい」とも言える。
ミ ああ、そう! そうですね。
泉 実際、ちゃんとそういう「キャラとの距離感」を作れている声優さんのほうが好感を持たれやすいですし。そう、さっきしていたアンソニー・ホプキンスとレクターの関係の話じゃないですけど、声優さんって「キャラクターに聞くような質問をインタビューで自分に聞かれる」のって嫌がりますからね。
思 ありますねえ。
泉 「それは原作者の方に聞いてもらわないと……」としか答えようがないですしね。せいぜい、「自分とキャラクターでここが似ていると感じる所はありますか?」くらいの質問ならOKなんだろうけど、それも「強いて言えば」とか「全然正反対なんですけど」って答えになりがちですしね。ベタに同一視することが許されるのは、本当に大御所声優くらいのもんで。普通はそこまでキャラと一体化しない。あくまで「演じさせてもらってます」っていう立場じゃないかなと。
ミ はいはい。
泉 そうじゃないといけないのが、二次元のキャラクター。そのくらい、「作られている物のなかに真実を見出すこと」が重要視されていて、そこにリアルを混ぜちゃいけない。って、考えていくとですね、左下の「二次元キャラ」から右上の「生モノ」まで、声優関連のコンテンツを一直線上に並べてるのは、そういう意味なんですね。
思 あ~あ~。

泉 ラブライバーが二次元オタクからすると、厄介オタク扱いされているのはそういうこと。
ミ へえっへ(笑)。ヤバい! こうして理論的に説明できちゃうんだそれ。なるほどねえ!
思 理論的に殴ってきますねえ(笑)。
泉 ゲームとか、アニメキャラとして出てくる「アイドルのキャラ」は、左下にある「二次元キャラ」の輪に含まれるんですが。そのコンテンツを、いわゆる「二次元声優アイドル」として見直すと、二次元の部分と声優の部分が半々で表に出てくるから、位置が真ん中になる。
思 ふ~む。
- ここで言う「二次元声優アイドル」が行うライブでは、「モニターにアニメ(二次元)の映像を流しながら現実の声優がパフォーマンスする」という画が典型的だと言える
泉 で、アニメの声優さんというのは、自分が演じている二次元の世界に引っ張られて見られる所がある。あんまりよくない話しますけど、声優グラビアというのは「本人のビジュアルがそこまで強く求められなくても成立する」っていう、そういう流れが作られていて、それを見るファンが「世界一かわいいよ!」って言うのがお約束になっている。
ミ なるほど、確かに(苦笑)。
泉 声優さんのビジュアルは半目にして見てる、半分はアニメ的な存在だと思って見れるから、全然褒めてくれるという。で、それが「アイドル声優」という肩書きに進むと、ビジュアル面を見る目は厳しくなってきますし、逆に声優のほうが副業みたいになってていいポジションにもなる。
ミ はいはい、ありますねぇ。そういうアイドル声優。
泉 代表作になる人気キャラをちゃんと持ってる人でもいいんですが、演じているキャラクターに強く依存しなくても成立するのが、まぁアイドル声優。
思 なるほどー、この斜めの対角線って、そうなってるんですかぁ。
泉 そして二次元オタクから見ればそのー、右上の対角線へと離れていくほど、そのオタクを見下したいわけですね。オタクが二次元から離れていくほど、厄介者扱いする対象になっていくという。
ミ なるほどねえ(笑)。
思 左下を起点にして見てみると、その距離で……っていう。
泉 まぁ、アイドル的じゃない人気の声優さんって多いので、声優オタク全般がラブライバーより嫌われやすいってこともないかな……と、作ってから思いましたが。それにぼくは、これでルッキズムがあるんだっていう話をしたいわけではない。実際ですね……これは漫画の話なんですけど、『彼氏彼女の事情』という少女漫画に、浅葉秀明という美男子のキャラクターが出てくる。
泉 イケメンで女好きなんだけど、なんで女好きなのかっていうと、「どんな女の子でも美少女に見えるから」っていう、本人の主観が理由だったってことが最終巻で明かされるんですね。

ミ は~、そうなんだ。
泉 アニメ化された時には拾われてない設定なんですが、原作ではそうなってて。「世界に不美人がいると思ったことがない」っていう特殊な目を持った人で、だから女の子なら誰にでも優しくしてるってキャラなんですよね。この浅葉秀明みたいな視覚世界で見ていれば、全然平和なわけで。実際、「二次元を介して声優を推している人たち」っていうのは、ある意味、浅葉に近い世界で人を見ているとも言える。
ミ へえ~。でもそういう人は特異というか、少ないでしょう?
泉 でも、これがイラストレーターさんとかでもいるんですよ。「どこにでもいるような女の子」を自分で感じたまま絵にしてるだけなんだけど、ファンには「こんな美少女、現実にはいない!」って褒められるから、「美少女を描いている意識はないんだけどなあ」「自分にはこう見えてますけど」って言う人。
- そうした絵師さんの発言については、この号に寄稿した拙論でも触れています
ミ なるほどね、まさに先ほど仰っていた、浅葉秀明に近いわけだ(笑)。
泉 そういう視点もすごい分かる。実際、生モノが好きな人って、多かれ少なかれ、そういう視点を持ってると思うんですよ。声優オタクにかぎらず。
思 あ~。
泉 これは重要な所だと思うんですけど、現実の人間って、どんな美女であっても、絶対に誰かに一度はブサイクって言われたことがあるんですよ。
思 うんうん。
泉 これはマジな話で、そうだな、エマ・ワトソンとかでも人前に出ているかぎり、絶対ブサイクって罵られたことはある。しかも単なる嫉妬で言われるってだけじゃなく、人間の顔って「ブサイクだと思って見ようとすればブサイクに見える」と思うんですよね。現実の顔って、子どもが少しずつ順応して見慣れていくものだっていう話をしましたけど、やっぱり生まれた後になって知る、「無理やり見てる世界」なんですよ。
思 うん。人間に見えているものが、認識に合っているものではないということですよね。
泉 元々、見たくて見てるものじゃないから、眼球から脳に入ってきたものを美しいと思うこともあれば、目に入ってきただけでグロいと感じても別に不思議ではないと思うんですよね。「本当は、動物のぬいぐるみみたいな感覚の世界に生まれてきたはずなのに」ってのが赤ちゃんの本音なんじゃないかな、ってぼくは思うんですけど。
思 それは言ってみれば、見てるものに対する情報のフィルタリングというか、変換の仕方みたいな回路が、「リアルなもの」と「二次元的なもの」では別々だから、単一の回路で見ようとすると違和感や拒否感が先立ってしまうということじゃないでしょうか。
泉 そうそう、超高解像度の映像データをいきなり送りつけられて、それをうまくコーデックできるかは人によると思うんですよね。
思 うんうん。
泉 で、レンダリングに失敗して、めっちゃガビガビの映像を見せられているのかもしれない。
思 うんうん、そういう人はもっと、情報量の少ないデータで見せてもらったほうが、「あっ可愛いな」ってなるかもしれないですよね。
泉 さらに言えば、「人間の脳にもっと合うような見やすい形に変換しよう」という理想を込めて描かれるのが二次元の絵なんだという。でも逆に、いい部屋持ってる友達のとこに遊びに行って、「お前、4Kのこんないい画質でテレビ見てたんか」って驚くこともあるじゃないですか。「俺の見ていたテレビと違う!」っていう。
ミ あ~! それ、同じゲーム遊んでても体験しますよね。高画質すぎて、「俺とは違うゲーム遊んでるんじゃないか?」って思ったことありますけど。なるほどね、そういうのに近いんでしょうね。
泉 で、これってマトリクス図における縦軸、「外面」の話をしてきましたけど、横軸は「内面」が変化しますよね。その横軸で考えても、内面が「本物」であるほど二次元オタクには嫌悪の対象となるし、VTuberオタクからすれば「そこにこそ魅力があるんだ」っていう。
ミ うーん、なるほどね。
泉 そこで分かりやすいのが、二次元オタクって、VTuberオタクをバカにしたい時に「バチャ豚」って呼び方をするんですけど。バーチャルに喜んで貢いでる連中、みたいなニュアンスですね。
ミ あーはい、最近多いですよね。
泉 あれって実は一方的にバカにしてるわけではなくて、相手を自分たちのレベルに落としてるだけなんですよね。二次元オタクは「萌え豚」って呼ばれてきたわけだから(笑)。「萌え豚のバーチャル版」でしかなくって、一方的に貶めることができてない。
ミ な、なるほど(笑)。
思 ふふふ(笑)。
泉 似たようなもんなんだけど、「俺たちはナマには貢いでないぞ」っていう、まぁそこだけが違うっていう話なんですね。あと、ビジネス的な話もすると「VTuberオタクよりもアニメオタクのほうが圧倒的に多い」ってことも直視しないといけない。
思 それは、VTuberの将来を考えるならってことですか?
泉 そうそう、ここまでは「分析」の話をしてきましたけど、コンテンツ業界として見た場合、ミミムさんにも考えやすいんじゃないですか? これからコンテンツ展開していくというか、マーケティングの話ですよね。
ミ あー、はいはい。
泉 こうやって分析していかないと、VTuberの外のジャンルって議論の俎上にも上ってこないんですよ。
ミ 確かにね。その、マーケティングをするためにはね、ターゲットがどこにいるのかを明確にしないと話になりませんからね。
思 ましてやそのファン同士で、嫌悪感や違和感を持つ人が多いのなら、しっかり狙いを定めないと「刺さらない」で終わるかもしれないわけですよね。
ミ そうですね。
泉 「ぼくら語り」をすることで「いないことにされる」問題っていうのが、ここにもあって。二次元オタクがいないことにされてしまう。「オタク=VTuberオタク」っていう、ぼくら語りになってしまうわけですよ。
ミ それは不味いですね。こう考えていくと、全然違いますもんね。
泉 KAI-YOUの記事でも書いたつもりなんですけど、「VTuberがオタクにとってめっちゃブームになってる」という気分になるのは、まやかしの昂揚感であって。オタクがみんなVTuberを好きなわけじゃないのに、「オタクならみんな分かるでしょ?」っていう勘違いをしちゃう。
ミ はいはい、それは……ありますね(苦笑)。
泉 それがよく出ていたのが、2019年の「ぽんぽこ24 Vol.3」内でVTuber有識者会議があった(7時間3分頃~)んですけど。「今後、個人勢とかVTuber全体はどうしたら伸びますかね」っていうテーマになった時、「やっぱり登録者数とか頭打ちになってるから、外に出ていくしかないですね」って口を揃えるんですね。で、その「外」とは何かというと、「一般層」って言うんですね。でなければ「海外」とか。
ミ あ~、あ~~っ! 「マスに訴えかける」は……、みなさんが今まで何度もやられてることですね。
泉 「二次元オタク」を見ないフリをすることで、「オタクの外」っていうともう一般人しかいなくなるってことなんですよ。VTuberオタクの外には、二次元オタクもいれば、声優オタクもいるし、色んなオタクがいる。でも、それらは「いない」ことにされてるから、「じゃあオタクのなかでは頭打ちだし、残るは一般層ですよね」って結論しちゃう。
ミ あー。自分もその……思考のワナに引っかかったことあるわ、うん。
泉 その結論に至るまでに、いかにもの凄いバイアスが掛かってるのか、ってことなんですよね、無自覚なまま。
ミ うん。あったあった、そういうの。企業さんが絡むので、自分からはあんまり言えないけど(苦笑)。そうなんですよね。「VTuberの登録者数には、オタクという層が全て含まれている」という勘違いを起こしてたってことですよね。じゃあそこから先は「マスに訴えよう」になってしまう。確かにそういうのはありますね……。
思 実際のところ、私も「VTuberのファン層ってどのくらいいるのかな?」と思って試算してみたんですけど、一年前に出した記事でも、たぶん150万人くらいじゃないかなと見てるんですよね。
泉 確か、その記事で一緒にアニメファンの総数も試算されてましたよね?
思 そうなんですよ。アニメファンのほうは、アニメ視聴者が日本に3000万人いるという統計データが出ていまして。つまり当時の数としては、そのせいぜい5%くらいしかVTuberにハマっていないわけです。
ミ 見向きされてないと。
思 そうです。だから、外に出ていくならまずそこなんですよね、たぶんね。
- 当時の泉(と卯月コウ)のリアクション
有識者会議裏実況、メディア側の識者の分析が「現在の客層は頭打ちだから、その外(一般層)から新規獲得しないと」という見解に留まってるのに対して、企業勢側のコウが「一般層から新規獲得はできてないけどオタク層は全然頭打ちじゃない」って返しててそうそうってなったhttps://t.co/Q39AMITOOn
— 泉信行 (@izumino) 2019年8月18日
泉 今の二次元オタクにとって、一番デカい課金対象というと、アニメよりもソシャゲになるのかな? 経済規模的には。
ミ ソシャゲでしょうね。中国のbilibiliでもFGOの恩恵は相当大きかったですし。じゃ、まぁ19年に「頭打ち」とか言われてても、「新春21年予測」としては「これからまだまだ伸びるぞ」というのもあり得ると?
思 その余地はあるけど……ですよね?
泉 そうですね。去年(2020年)は業界全体が一般層というより、海外を強く意識させられていた年なんですけど。実際にVTuberを運営してる人たちが、こういうオタク層についてどのくらい考えて戦略を決めているのかはともかく……。去年の9月に「ホロライブEnglish」を始めた、カバーの海外戦略っていうのは環境的にも恵まれてまして。
ミ はいはい。
泉 大きい主語を使うと、「日本の一般層」に向けるのは将来性があまりないから、「海外」に向かえばいいんだと。でも、ホロライブが訴えかけてるのは「海外」じゃないですよねあれ。「海外の日本オタク」なんですよ。
ミ そうそう、そうですね(笑)。日本オタクですね。元々、日本の二次元コンテンツに親しみのある人たちが海外には多くいて、それを取り込んでいる感じですよね。
泉 日本語がちょっとしか分からないなりに、日本発のコンテンツが好きな二次元オタクなんですよね。
ミ そう! 一般人ではない。海外の一般人をターゲットにしているわけではない。
日本発の二次元エンタメで、
採用 | カバー株式会社
世界に出よう。
泉 以前から、「海外の日本オタク」を育ててきたオタクカルチャーに感謝すべきであって、欧米人を、全く何もない所からホロライブやVTuberの文化が魅了したわけでは決してない。
ミ そうですねー。ハリウッドで『マトリックス』が作られたのも、日本の『攻殻機動隊』のおかげだったりね。
泉 そういう海外の「日本産の二次元大好きオタク」という層のなかに、「VTuberは生きてて会話できるから可愛い」というブレイクスルーを起こす人と、起こさない人がいるということなんですよ。
思 ふわっとコンテンツが広がった時には、土台になるファン層が、ちゃんと別のコンテンツによって整えられていて、その土壌があってこそ芽が開くということなんでしょうね。VTuberは2018年頃にも海外で注目されていましたし、そこから今のホロライブの人気も一気に広まっていったと。
ミ ホロライブが元々中国で展開していたのも、日本の二次元コンテンツの「地ならし」が長年あっての人気でしたからね。突然、一般層にバッと人気が出たわけではない。確かに、日本のアニメが長いあいだ消費されてきた経緯というのがあったから。
思 そうですよねえ。
泉 (「中国の一般層は、二次元のイラストにあまり抵抗感がないらしい」という話になって)……日本だと、銀行の通帳とかクレジットカードに、ディズニーやスヌーピーのキャラが使われてても、そんなに嫌がる人ってあんまりいないですよね。
ミ そうですね、中国の二次元イラストって、そのくらいの認識をされてると思います。
- 日本人が中国に住むと嫌がるが、実は中国人はあまり気にしてないらしい「洛天依キャッシュカード」
今日銀行口座を作ったら、このカードを渡された。「変えられないんですか」と聞いたところ「もう登録しているから変えられない。期間限定バージョンだ」と。頼んでいない。カードで買い物できない。 pic.twitter.com/2fzxSItaZP
— 上海三年目 (@chinalogisearch) 2020年11月25日
- 日本のスヌーピーカード
/
— 三菱UFJニコス (@mufgcr_official) 2021年8月10日
Happy Birthday🎂
Snoopy! August 10!✨
\
三菱UFJニコスが発行しているスヌーピーカードがリニューアルしました🎉
👇🏻くわしくはこちらhttps://t.co/7FYLzA6adF#スヌーピー #ピーナッツ #HBDスヌーピー #snoopy #peanuts #HBDsnoopy pic.twitter.com/I4KyeDYTMC
泉 でも日本だと、スヌーピーと美少女のイラストは完全に別物だということになってますよね。だからそれで、Twitterがたまに荒れたりするわけですけど。ラブライブと沼津のコラボの件とか。
ミ ねえ(苦笑)。
【沼津】JAなんすん様より熱いオファーを頂き、本日、高海千歌が『西浦みかん大使』に就任致しました!!
— ラブライブ!シリーズ公式 (@LoveLive_staff) 2020年2月12日
千歌ちゃんに代わって高海千歌役・伊波杏樹が、ららぽーと沼津にて行われた大使就任式に出席しました。
これからも沼津のみかんを、地元の元気を世界に伝えていきます!!🍊🍊🍊
#lovelive pic.twitter.com/gcqbnyHriR
泉 そうそう、だから、「二次元オタクがリアル方向を嫌っている」という話をしてましたけど、当然、現実が好きな人たち……この図の上側の人たちも、その一部は下側の二次元をめっちゃ嫌っているという。
ミ ですよね。逆もあるっていう。
泉 スヌーピーの絵柄みたいに、完全に「作り物」に振り切っていれば見逃されるのかもしれませんけどね。でも、二次元オタクに好まれるキャラというのは、解像度高めに見えるわけですよね。現実側の人たちから見てもそうだろうし、実際、絵のデータとしても細かい質感が好まれるわけですけど。
ミ あー、はいはい。身体的特徴も、はっきり見えますからね。スヌーピーとかに比べると。
全体の締めくくりと、図の下側の解説
泉 そこで最後に、皆さんに感じてほしいのは、このマトリクス図を見ていただいた上でですね。VTuberファンとか、VR住人の肩身の狭さを感じてもらった上で、これからどういう戦略が必要になってくるのかということを考えていただきたい。
ミ ははは(笑)。いいですねえ、すばらしい。
思 あ、そこでちょっと聞いてみたいんですけど、下側の真ん中にある「ナラティブ型VTuber(VT)」というのは何を指してるんでしょう?

泉 そうだ、説明を忘れてた。じゃあ、細かい部分の解説に入っていきますか。
思 お願いします。
泉 えーと、この「ナラティブ型VTuber」というのは由来があって、「ReVdol!(リブドル)」というプロジェクトが公式の自称として用いている(※当時。現在は解散済)「ナラティブ型バーチャルアイドル」から採ってます。
ミ は~、これリブドルからなんだ。
泉 最初からは名乗ってなくて、確か去年の「京まふ」あたりからじゃないかな? 突然使い始めたのは。
泉 その活動内容からしても適切なネーミングだし、この「リブドル型」と言えるスタイルをちゃんと成立させているVTuberというと、確かに「リブドルが先陣を切っている」はずだし完成度も一番高いので。そのスタイルの第一人者が「ナラティブ型」というフレーズを使うのであれば、「リブドルに近いVTuberのスタイルはナラティブ型と呼んでいいだろう」という分類をぼくはしてますね。
思 すみません、私はあまり詳しくないんですけど、「ReVdol!」というのはコンテンツの名前なんですか?
泉 そうですね。中国から展開していて、原語版のプロジェクト名が「战斗吧歌姬!(じゃんどうばあぐうじい)」、「戦え歌姫!」って意味の中国語なんですけど、日本で展開するには「战斗吧」だと伝わりにくいので、海外展開用に決まった名称が「ReVdol!」です。
ミ 非常に、よくできたコンテンツだと思います。日本人のファンも結構いらっしゃるとよく聞きますね。
泉 で、何がナラティブ型なのかというと、たぶんゲーム開発用語の「ナラティブ」のニュアンスが入ってると思うんですけど、「ゲームを通して物語をどう伝えるか」を考えるための用語ですね。リブドルに参加しているクリエイターさんも、菊池たけしさんというプレイ・バイ・メール(PBM)やTRPGの業界で知られたライターさんが入っていて。「ファンの反応によってインタラクティブに物語が変化していく」っていうシナリオに対応できる人をメインライターに据えてるんですね。
ミ あー、そりゃすごい。
泉 しっかりしたSF的な物語を3DCGアニメとして制作しつつ、「その物語の登場人物が本人としてバーチャルアイドル活動をする」という。だからメインヒロインの子は「李清歌」という名前なんですけど、アニメ版のクレジットは「李清歌役:李清歌」と書いてあるんですよ。
- リブドルの制作体制に関しては『CGWORLD』の特集やWeb記事に詳しい
泉 そういう、「脚本家の考えた物語」という作り物のシナリオがありつつ、そのシナリオから逸脱した「ライブ配信を行うバーチャルタレント」としても成立するという点で、位置的にここ(下側の中央)かなと。
思 はあ~。
泉 外面的には、全てCGだから虚構の作り物(縦軸の下側)。内面的には、ライブ配信におけるリアルな内面とアニメ版における虚構の内面を併せ持つからリアルと虚構のあいだ(横軸の中央)。で、このナラティブ型のなかに入れていいと思うのが、avexの「言霊少女プロジェクト」(※2021年活動終了)であったりとか。あとリブドルや言霊少女よりもずっと前から続いてますけど、「22/7(ナナブンノニジュウニ)」も「アニメやゲームの物語」がありつつ「キャラクターがリアルタイムでアドリブの出演ができる」と。
ミ (「言霊少女」のプロジェクト的な失敗の話になって)……先ほどのマーケティングの視点が、見えてなかったっていうことですよね、ここは。各クラスタに分けて需要を分類するのではなく、「二次元オタクとVTuberオタク」をいっしょくたに考えてしまったがゆえの結果。そのひとつの形と言えるのかもしれませんね、もしかしたら。
泉 そうですねえ。VTuberブームに乗っかろうとしても、そのブームは局所的なオタクの話でしかない、ってことに気付こうとしなかったというか……。これは元々、お蔵入りしていたプロジェクトを掘り起こして再利用しようとしたIPなんですが、そもそもが「二次元オタク向けに企画していた時点で成立に至らなかった」タイトルなわけですから、そもそもがオタク相手に勝負できてない。
思 ブームに乗っかるというのはやはり難しいんですねえ。
泉 逆にブーム的な潮流と、元々の環境がわりとハマったのが「22/7」なのかなと。計画時から「リアルアイドル」(分担的にはSony Music)と「アニメコンテンツ」(分担的にはANIPLEX)の両面で行こうとしていたという点では、リアルアイドルとラブライブの中間くらいの土壌があったわけですけど。その上で、VTuberブームが来る前の初期段階から、「キャラクターをアドリブで出演させよう」っていう意図はあったみたいなんですよね。
ミ へー、そうなんだ。
泉 結果的に、2018年から「22/7計算中」という冠番組のバラエティ番組を放送しはじめたことで、VTuberと変わらない、「ナマのリアクションやアドリブの部分を活かした」バーチャルアイドルの方向へと完全に舵を切ることになるんですね。そこは番組のコンセプトとメンバーの資質がガッツリとハマってたからこそ実現したことで。
ミ はあ~。
泉 そのビジョンのある無しが言霊少女との差になっている。言霊少女は、声優をパーソナリティにしてキャラクターをゲストに呼ぶWebラジオはしてましたけど、二次元の姿を活かすという意味では、本人たちがSHOWROOMで雑談配信するのをほったらかしてただけですから。それはかなり見てて辛い所があった。
ミ ヤバいと思いますね。やってる子たちも大変だろうし。
泉 一応、物語はあるんですよ。「少女たちが学校でラップの部活を作る」っていうWebアニメはあるんだけど、そこに出ていた子たちが個人で配信するSHOWROOMと、ラップで部活しているアニメ本編が地続きになってるとは感じにくくて。
ミ なんかそれは違うなあってなりますよね。
泉 「22/7計算中」の場合は、22/7というバーチャルなアイドルグループが「アイドルとしてレギュラー出演するアイドル番組」として制作されているというテイがあるからファンも入り込めるんですよね。
思 なるほど……。ライブ配信をどう、コンテンツ自体の物語に組み込むかが問われてきそうですね、それは。
ミ じゃあ、次はこの「ナラティブ型」以外のも見ていきましょうか。
泉 えーと、ナラティブ型の周辺から進めていくと……(「ARP」、「バーチャルYouTuber可憐」、「にじさんじSEEDsの海夜叉神と出雲霞」の順に解説を加える)出雲霞は「VTuberを利用して物語を語った私がいたからといって、他のにじさんじのバーチャルライバーもみんなそういう存在だと思う必要はないし、こういうのをするのは私だけだと思ってほしい」とファンに告げて去っていったんですが。特殊な立ち位置でありつつも、彼女がにじさんじ所属のバーチャルライバーであったのも事実なんですね。だから「ナラティブ型VTuber」と「一般的なVTuber」というのは、こうして地続きに連続しているのかなと(※図では「海夜叉神」がVTuberの輪と重なっていないのだが、配置の意図としては出雲霞と同じく「VTuber」に含めているつもり)。
思 ふ~む、こうして見るとVTuberもまだまだ色んな可能性があるのが分かってきますねえ。
泉 で、この図だとなんで「VTuber」が「アバター」より左にズレてるかというと、VTuberには「現実にはどう考えてもありえないプロフィール」を持つことがあるからで。あと性自認とかそうかもしれないな。見ていて「プロフィール上の性別が信じられなかったとしても、プロフィール上の性別に従って付き沿わねばならない」のがVTuberだと思うんですよ。そこで「バ美肉おじさんなんでしょ」とか、その逆なんでしょとか「リアルにいる人間の内面や性こそがその人の内面や性である」という前提で言っていいのはアバター文化の領域なので(※ここも「VTuber」と「アバター」の輪は重なっているつもり)。
ミ まぁそうですね。
泉 性別と違って、VTuberの公式年齢だけは「実は十代じゃないんでしょ」とかネタに昇華されがちなのは面白いですけどね。あと、二次元オタクのプライドに近いものを抱えてるVTuberオタクも結構いるんです。「VTuberに裏で恋人がいたとしても俺は別に構わない」みたいな、変な意地の張り方をする人がたまに。
思 あぁ、「表に出すな」っていう(苦笑)。
泉 「彼氏がいたら俺は耐えられんかもしれん」という人もいれば、「俺もガチ恋だが、バーチャルな姿にガチ恋してるんであって、配信に出さないのであれば裏で彼氏いようが子持ちだろうが俺は全然いい」って言える人は、心に多少、誇り高い二次元オタクの血が入ってるんです(一同笑)。
思 これも、虚構の延長として見るか、リアルにあるものとして見るかで受け取り方が違ってくるんでしょうねえ。
ミ 確かに。それも「外面のリアル」を見るか、「内面のリアル」を見るかでも違うでしょうし。
泉 二次元オタク的なプライドで言うと、「現実の人間を含めてガチ恋するのか」という問いは、「生身の人間を性的消費の対象にするのか?」という倫理的な問いに繋がるんですよ。「所詮はキャラクターでしょ」って、VTuberを軽視してるわけでもなくて、実在する人格に敬意を払うからこそ、一歩引いた付き合い方になる。二次元オタクが、声優さんに「キャラクターに息吹を吹き込んでくれる人」として払う敬意と同じなんですね。
ミ はいはい。
泉 ただ、それはそれで「お前、あえて客観的に見ようとしすぎじゃない?」という違和感もありません?
ミ あー……。まぁ、そこは本当に人によるんでしょうね。
泉 「いや、この人はめちゃくちゃ自分の素をさらけ出していて、それでいてプロフィールとも整合性取れるし、内面のリアルさについては疑う余地ないんだけど」って感じられるVTuberに対して「俺はそんなのどうでもいい」って言うのは、その内面も含めて応援しているファンもひっくるめて、失礼な態度になるかもしれませんよね、モノによっては。
ミ あー、はいはい。
泉 VTuberにかぎらず、「あれは全然ビジネスでやってないでしょ」っていう身を削るような活動を続けている人に向けて、ことさら「いやビジネスでしょ」って決め付ける行為にも似てますね。
ミ 確かに。
泉 そういえば、アバター文化のほうだと、特にのらきゃっとさんなんかが見事に一歩引いた尊敬をされてる方ですよね。ファンは「のらきゃっと」にガチ恋しつつ、「のらきゃっとを作り出している人」には敬意しかないっていう。そこの作り込みは本当に徹底してる人だから。
思 ええ、プロですよねぇ……。
泉 でもそれはVTuberとは対照的。「のらきゃっと」自身の内面、というのは本当はどこにもない虚構であり、リアルな内面は「のらきゃっとを作り出している人」にしかない、という厳粛な区別をしているわけです。
図の右側の解説
泉 右上の左寄りにある黒いアイコンが何かっていうと、綾小路翔ですね、これ。

ミ あっ、そうなんだ? 「別名義タレント」ってそういう意味なんだ。
泉 つまりDJ OZMAに対する綾小路翔ですね。まぁそのどちらにしてもプロフィールの虚実が曖昧なアーティストなんですが。「プロフィールが現実離れしている芸能人」っていう分類ではデーモン小暮がメジャーですけど、デーモン小暮は「デーモン小暮ではない誰か」が現れて「あれは自分だよ」と証言したりするわけじゃないのが違いですね。あくまで「デーモン小暮=デーモン小暮」なんで。
ミ そうですね、ピコ太郎に対して古坂大魔王が出てくるなんてことは、デーモン閣下だとならないですね。
泉 名義の違う別人が出てくるという意味では、「森昌子の姪」の「ま~ちゃん」なんかもここに入れたいですね。いずれにしても外見的には三次元のままで、内面的には別の人格、つまりウソらしき要素が混ざることが比較によって分かる。「デーモン小暮=デーモン小暮」だとその比較しようがないし、極論すれば「もしかして本当に自分を悪魔だと思ってる人なのかも」と思われてもいいですからね。
ミ なるほどね。
泉 続いて右端も、上から見ていきましょうか。まず「生モノ」にそのまま重なってるのが、「顔出し主」です。まぁ文字数を縮めるために「生主」みたく書いてますが、歌い手でもYouTuberでも、配信者全般を含んでます。
ミ はいはい。
泉 そして顔出し主がいれば、「顔出しNG主」もいる。実写でカメラ配信はするんだけど、首から上は見せないとか。胸から下だけ映してASMRする女性配信者とかが分かりやすいですけど、「弾いてみた」系のアーティストや、料理系のYouTuberなんかでもよく見ますよね。
泉 「ナマの顔を見なくてもいい」って意味では、二次元オタクにも多少見やすくもなっている。で、顔出しアリとNGのあいだに入れてあるのが「コスプレイヤー」。これは「外面のリアル度」という指標(縦軸の高さ)では、左側の「2.5次元」に近いと考えています。
ミ はいはい。
泉 レイヤーさんは「顔は出しつつコスやメイクで二次元寄りに体を近付けている」という意味では2.5次元に近いですけど、2.5次元の舞台に比べると、レイヤーさんはレイヤーさん自身が主体なので、内面はリアル。
ミ うん、そうですね。
泉 「アバター」のすぐ上にあるのが、「似顔絵主」。これも、ニコ生主とか、キャス主とか、歌い手やYouTuberとか配信者全般をひっくるめてます。そっくりな似顔絵ってわけじゃなくて、その人のアイコンや立ち絵に使えるような「イメージイラスト」を主に用いて活動している人たちですね。その二次元の絵にプラスして、「顔出しNG主」と同じようなカメラ配信もたまにやるような。
ミ うんうん。
泉 決まったジャンル名とかない分野なので、便宜的に「似顔絵・アイコン主」とか、「似顔絵配信者」とかぼくは説明する時に呼んでます。この世界から、最もデカいコンテンツに育ったのが「すとぷり」ですよね。
ミ あ~っ。うんうん。
泉 すとぷりは、ネットで見るかぎりには似顔絵主のようなことをやってるんですけど。ちなみに、戌神ころねのイラスト担当であるフカヒレさんが手掛けていたキービジュアルもあって。
この1年間で制作させていただいたすとぷりの等身イラストです🍓 pic.twitter.com/343VffVAmU
— フカヒレ (@fuka_hire) 2020年9月17日
思 へぇ~っ。
泉 知らない人からすると、「へぇ~」って思うでしょ? 絵柄的にはほとんど同じ位置にあるのに、「VTuberとは全然関係ないジャンル」ということになっているという。このイラストも、みんなコンビニで見たことあると思うんですが。
🍓👑すとぷり×ファミマプリント✨
— ファミマプリント【公式】 (@famimaprint) 2022年1月25日
\ラスト👏第三弾⭐️️販売開始📣/
大好評販売中のすとぷり5th Anniversaryブロマイドは遂にvol.3😍🎶
1/25(火)10時~2/21(月)23時59分までの期間限定!
お見逃しなく‼️
詳細はこちら↓
https://t.co/Y0WVYeCbAB #すとぷり #ファミマプリント pic.twitter.com/VhZAmawbZ2
- ちなみに最近はnanaoさんのキービジュアルがメインになっている模様
ミ 面白い! 要するに、「実は見た目だけの問題ではない」ということですよね。
泉 んで、すとぷりは「リアルライブの時だけ顔出しをする」というユニットで。実写動画を出す時も、「顔の部分にだけ似顔絵アイコンを貼る」という編集をする。
www.youtube.com
www.youtube.com
泉 こういう活動によって、アイコンは「あくまで本人をイメージした(※似てるのかはさておき)絵」であって、本人は現実にいる人間だし、「絵=本人」というわけではない、という印象が生まれる。「虚構」と「リアル」が明確に区別されやすくなるという点では、アバター文化と同じ流れを汲んでいるとも言えます。
思 ふ~む。
泉 逆にVTuberは、「二次元の姿こそが本人であり、画面の向こうで生活しているのもその二次元の姿なのだ」という印象を生み出そうとするのですが、そこが似顔絵主との大きな差となりますね。で、最近ようやく(※当時)、すとぷりも「バーチャル化」するらしいんですよね。
- この配信の3ヶ月後に開催された3Dライブ
- すとぷりに続いたP丸様。の3Dライブ
ミ へっ?(笑)
泉 キービジュアルと同じデザインの3Dモデルを作って、バーチャル空間でライブするという。これ、活動の幅めっちゃ広いですよね。似顔絵主であり、リアルライブでは顔出ししつつ、ネットでは顔出しNGの実写動画を作って、3Dモデルでライブもできる。その上で、キービジュアルのグッズも作れる。
ミ ねぇ、特殊ですよね。
泉 他にも浦島坂田船、騎士A、いれいすといった「歌い手グループ」が近いファン層をターゲットにしていると思いますが、これらは明らかに、VTuber業界に並ぶ巨大コンテンツなんですよ。規模的に考えると。
ミ そうですね、動かしている力だと。
思 うん、チャンネル登録者でもすとぷりは100万人超えてますからねえ。
ミ でもこれ、「男VTuberは伸びない」ってよく言われますけど、すとぷりと何が違うんでしょうね?
泉 友達の女性オタクから話を聞くこともあるんですけど、確かに男のVTuberには興味なさそうな感触があって。そういう友達は大抵、「二次元も生モノもOK」っていう雑食タイプなんですが、同時に「二次元なら二次元の男性キャラ、生モノなら男性アイドルで満足してる」って感じがある。「その中間があったとしても別に間に合ってるから要らないんじゃない?」ってハッキリ言う人もいて。
ミ ほお?
泉 つまり、内面がないなら完全に「理想的なフィクション」であってほしいし、内面がリアルなら「現実にいる人間」であってほしい。別にそこは混ざんなくていい、みたいな。それは男性オタクの「萌え豚的なプライド」とはまた別の美意識だと思うんですが。
ミ あー、うんうん。
泉 男の二次元オタクは「三次元が苦手で二次元の美少女が好き」っていう価値観になりやすいですけど、女性オタクはそもそも、生モノに抵抗感がなくて両方イケるっていう人が結構多い。だから「VTuberは二次元なのにリアルな人格があって素晴らしいんだ」とVTuberファンが布教したくても、「リアルな人格ならもう推しがいますから」って断られちゃう。
ミ あ~。
泉 でも男オタクは元々「リアルの推しがいない」ことが多いので。そこに「作り物ではない、リアルな人格も推してみたい」という潜在的な欲求があると、今まで全く知らないジャンルとして「リアルな人格を持つVTuber」がスッポリ収まりやすいんだと思いますけどね。
ミ なるほど。
泉 その上で「VTuberも推せる」女性は少なからずいて、増えてきてると思いますけど。ただ、確率として「男性と比べて女性が少ない」となるのは、結局のところ、そういう生態の違いがあるからじゃないでしょうか。
終わりに
ミ で、配信の規定の時間は一応超えているんですけど、「オタクビジネスにおけるVTuberの立ち位置」というのを解説していただきまして、ここで区切っても大丈夫ですか?
泉 そうですね。なかなか、ニュアンスを伝えるのが難しいなあと実感しましたが。伝わりましたか?
思 ええ、これだけじっくり説明していただくと、やっぱり全体がよく見えてきますねえ。
ミ ねえ、まずこの図が一目瞭然であるというのと、なぜそれぞれのジャンルがそこの位置にあるのかという説明を付けていただくことで、「なんでこうなっているのか」を本当に分かりやすく説明していただけたと思います。
泉 やっぱり、伝えたいのは細かい部分を見ていくだけじゃなくて、「俯瞰的に広く業界を見てほしい」ということなので。
思 うんうん。「なぜ各クラスタ間で反目するのか」とか、これでよく実感できましたね。
ミ ホントですね。それは分かりやすかった!
泉 そのクラスタの区別も、いい意味と悪い意味が両方あるんですけど。「他の人たちがちゃんといますよ、そこに気を向けましょうね」というのは、単に対立するから気を付けろということじゃなくて……。逆に、「俺たちは独りじゃない!」ってことなんですよね。
思 ふ~~む。
泉 よく、「地球外生命体はいるのか?」って話になった時に、「我々は独りじゃない!」ってセリフに繋がるじゃないですか(一同笑)。他に文明が存在している、他者が存在しているかもしれないというのは、基本的に「いいこと」なんですよ。
ミ あっ、そうですね!
泉 戦争とかあるかもしれないんだけど、「知的生命体は人類しかいないんだ」って思うよりかは、夢がある。そこに何かの可能性があるかもしれないっていう。そういうビジョンも見えてくるという意味では、「外に目を向ける」「そこに実際に人がいるんだと感じる」という行為はとても大事なことじゃないかな? と、いう意識があってこういう話をさせていただきました。
ミ 確かに。これはもう、最高に面白かったです。それは充分に伝わったと思います。
泉 さらに言うと、「一緒に成長していけるのか?」ということですね。「VTuberシーンの成長」じゃなくて、オタクの全体的な文化圏として。
ミ なるほど、それは大きいメッセージですね。
泉 すみません、図を説明するのに時間かかりまして。
ミ いや、かなり勉強になりました。知らないコンテンツも結構多くてね。学芸大青春とか始めて知りましたよ!(※文字起こしでは省略)
思 私も凄く勉強になりましたね……。ホントにこうやって実例を並べると、「現実とリアルの中間」を目指して攻めているプレイヤーにも、色んなアプローチがあるんだなあと分かりますし。
ミ ね。これも俯瞰しているからこそ見えるマップだと思うんですけど、それぞれの哲学であったり、プロデュース側の方向性だったりがあって、このように散らばっているということですよね。この散らばり方を見ることで、それぞれのターゲットも分析できるし、未来を占うことも可能になるということですよね。
思 ですねえ。
泉 コンテンツホルダー側の視点で、実践に活かせそうだと思うのは、例えばホロライブのタレントが有名なゲームのアンバサダー役に指名されたりすると、異なるファン層がぶつかっちゃう場になるわけじゃないですか。
ミ そうですね。
泉 アニメイベントのMCにVTuberが起用されることもあって、その時に「ちゃんと相手を立てる」トークのできる人を連れてこれるのか、とか。VTuberにとってはアウェーなわけで。
ミ うんうんうん。
泉 主催側が「人気VTuberですよ、知ってるでしょ?」って当然のような顔して出すと、「出しゃばってくんな」って反感をもらいやすいなかで、どう好感を持たれるような対応ができるのか。
ミ なるほどね、つまり「VTuberをどのジャンルに展開していくと、どういうターゲット層とぶつかるのか」をちゃんと予想できないとダメだってことなんでしょうね。そのためにこういうマップを自分のなかに持っているかどうかが影響してくると。
思 そのジャンルの背後にいる、ファンの意識を理解できなきゃいけないんでしょうねえ。
泉 そうです。例えば「アンチには言わせとけばいいんだよ」という価値観は、同じジャンルに留まっている内だけ言えることなんですよ。勝手にアンチが付いたところで、よそ様に迷惑掛けてるわけじゃないですからね。ただし、「よその世界からどう見られているか」は、外に迷惑を掛けてないのか参考にすべきだと思いますけどね。
ミ そうですね。
泉 ちなみに「一般層に出なきゃ」って言う時の「一般層」っていうのは、「この図の右上のさらに外」と考えると、途方のないスケールの話だったことも分かりますよね。「推し」とかを持たない人たちってことだから。
ミ 確かに(笑)。かなり距離感ありますよね。
泉 「一般層に出る」って言う前に、隣り合ってる世界はこれだけ広いんだと。
ミ ねえ(苦笑)。


![HoneyWorks 10th Anniversary “LIP×LIP FILM×LIVE"通常版 [DVD] HoneyWorks 10th Anniversary “LIP×LIP FILM×LIVE"通常版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51e2Z2eR0SS._SL500_.jpg)
![Animage(アニメージュ) 2020年 01 月号 [雑誌] Animage(アニメージュ) 2020年 01 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61YGvlChxeL._SL500_.jpg)


![ハンニバル [Blu-ray] ハンニバル [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Js-f-fOTL._SL500_.jpg)

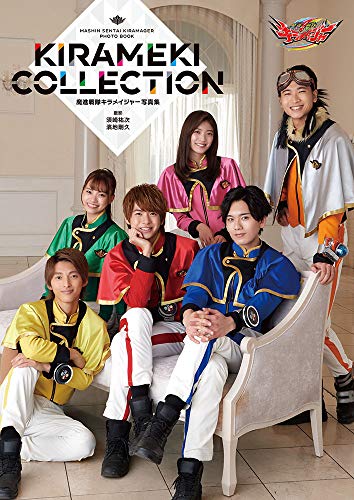




![レディ・プレイヤー 1 [Blu-ray] レディ・プレイヤー 1 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51vQiM8V0YL._SL500_.jpg)





